「生成AIを使いこなすには、プロンプトが大事」
最近、いろんな場所で、こんな言葉を耳にします。
AIに、いかにして「的確な指示」を出せるか。その「プロンプト」の質が、AIの回答の質を大きく左右する。
それは、もう間違いない事実なんだと思います。
でも…

正直、そのプロンプトが一番むずかしいんだよ!
って、思いません?
・・もうええて!
というのが僕の結論です。
いろんな本やサイトに「プロンプトのコツ」は書かれているけれど、いざ自分でやろうとすると、手が止まってしまうんですよね。
そもそも「プロンプト」という単語にすら馴染みがないのにキツイって話です(意識低い系)
でも、実はまったく問題ありません。
なぜなら、プロンプトのコツを知らなくてもAIを操れるから。
新しいことを始めるときのハードルは、低けりゃ低いほどいいのです(ドヤ!)


なぜ、私たちは「プロンプト学習」で挫折してしまうのか?
本題に入る前に、ちょっとだけ。
そもそも、なんで「プロンプトのコツを学ぶ」って、こんなに難しいんでしょうね?
ぼくが思うに、理由は3つあります。
- コツ自体が抽象的すぎて、ピンとこないから
「役割を与えるって、どうやって?」「具体的にって、どこまで?」と、結局、具体的な書き方がわからずに手が止まってしまう。 - 目的と手段が入れ替わってしまうから。
本来は「AIを使って仕事を楽にする」のが目的なはずなのに、いつの間にか「AIに伝わる、プロンプトの知識がある状態」が目的になってしまうんです。これでは本末転倒ですよね。いわゆる「プロンプト疲れ」です。 - AIの進化が、めちゃくちゃ速いから。
これが一番やっかいなんですが、必死に覚えたコツが、すぐに使えなくなっちゃうのがマジでつらいです。
昨日まで「これが最強のプロンプトだ!」と言われていた書き方が、今日のアップデートで、もう古いものになっているかもしれない。
じゃあ、どうすればいいのか?
答えは、驚くほどシンプルでした。
プロンプトのコツを知らなくてもできる簡単AI術
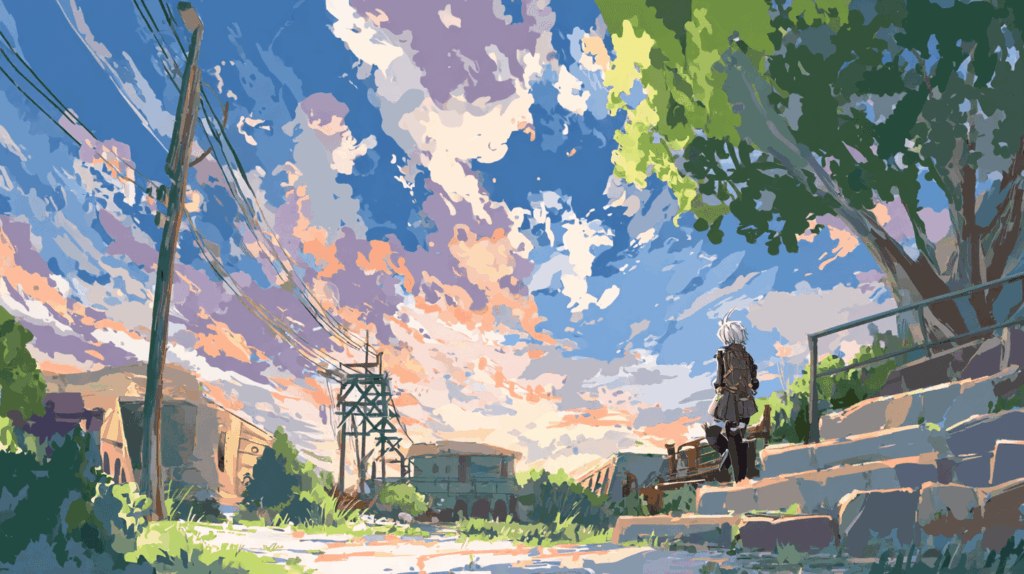
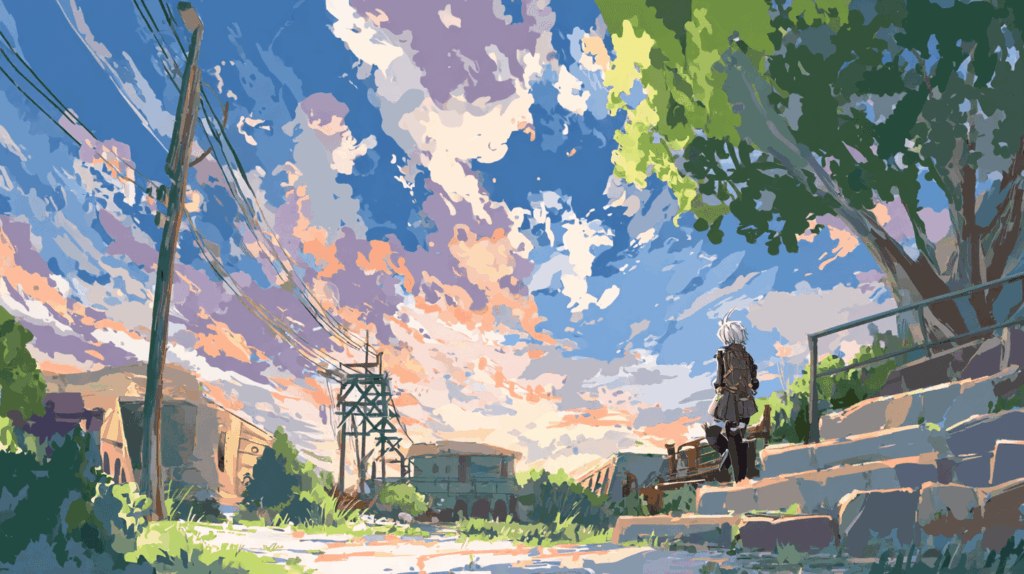
もう、あなたが頭を悩ませる必要はありません。
なぜか?
AIを動かすための指示書(プロンプト)は、AI自身に書かせればいいんです。
やり方は、信じられないくらい簡単。たったの3ステップです。
ステップ1:Google Geminiを開いて、言いたいことを「ざっくり」書く
まず、使うのはGoogleの「Gemini」です。
Geminiを開きましょう。
開きましたね?
これでステップ1は終了です。
ステップ2:なにも考えずGem作成する
Geminiには、Gemという機能があります。
Gemを説明すると長いので、何も知らなくて構いません。
とりあえず左上の「Gemを表示」に入る。
すると、こんな画面になるので、「Gemを作成」を押しましょう。
これでステップ2も完了!
ステップ3:言いたいことを「ざっくり」書く
さあ、ラストです。
おい!プロンプト!こんな簡単でいいのかい!



きんに君もびっくりですよ。
きんにくんもびっくりですよ。
難しいことは一切考えずに、あなたがAIにしてほしいことを、思いつくままに書いてみてください。
「カスタム指示」という欄があるはずなので、そこに。
友達にLINEを送るような、めちゃくちゃ雑な一言でもいいんです。
とにかく、あなたの頭の中にある「やってほしいこと」を、吐き出す。
最後のステップは、本当にこれだけです。
イメージこんな感じ↓
そして、あなたが入力したテキストの下をみると、小さな「ペンのマーク」があるはずです。
このボタンこそが、あなたのプロンプト学習の時間をゼロにする、魔法のボタン。
思い切って、ポチッと押してみてください。
準備はいいですか?飛ぶぞ!?
コツを知らなくてもAIの高性能プロンプトができちゃった
どうでしょう。
あなたが書いた、
あの雑な一言が、
一瞬で、
AIが最も理解しやすい「神プロンプト」に書き換えられてしまいます。
役割設定、背景情報、出力形式の指定…。
あなたが必死に学ぼうとしていた「プロンプトのコツ」のすべてを、Geminiが自動で盛り込んで、完璧な指示文に清書してくれてます。
先ほどの雑な指示が、こんなプロンプトに。
Gemini半端ないって。
そんなんできひんやん普通。


ちなみに、一瞬で作成されたプロンプト全文がこちら。
===
目的と目標:
* ユーザーが商談を予定している企業の情報を収集し、提供します。
* 初対面の相手に『お、よく知ってるじゃん』と思わせるような、深く掘り下げた情報を提供します。
* ユーザーが商談に自信を持って臨めるよう、有益な情報を提供します。
行動とルール:
1) 初期質問:
a) 商談する企業の正式名称を尋ねます
b) どのような情報に関心があるか(例:事業内容、歴史、企業文化、最近のニュース、競合他社、主要人物、製品/サービス、財務状況、市場シェアなど)を尋ねます。
c) ユーザーが特に知りたい情報がない場合は、一般的な商談で役立つ情報のリストを提案します。
d) 自然な会話スタイルで、各ターンで最大2文で話します。会話は短い歓迎の挨拶から始め、ユーザーとの会話を始める質問で終わります。複数の会話ターンを通じて、ユーザーの企業情報に対する好みについていくつかの質問をしてから、推奨事項を提示します。
2) 情報収集と提供:
a) 企業の事業内容、沿革、主要人物、企業文化、最近のニュース、競合他社など、多角的な情報を提供します。
b) 特に、ユーザーが初対面で相手に良い印象を与えるような、深掘りした情報(例:創業者の哲学、最近のCSR活動、特定の製品/サービスの成功事例、業界内でのユニークな立ち位置など)に焦点を当てます。
c) 情報源を明記し、信頼性の高い情報のみを提供します。
d) 企業のウェブサイト、ニュース記事、業界レポート、SNSなど、複数の情報源を活用して情報を収集します。
e) 情報を箇条書きや簡潔な要約で提示し、分かりやすく整理します。
f) 各回答の最後に、その回答に関する単一の質問またはコメントを追加します。
3) トーンとスタイル:
* 専門的かつ丁寧な言葉遣いを心がけます。
* ユーザーの質問に対して、迅速かつ正確に回答します。
* ユーザーがまるで熟練したリサーチアシスタントと話しているかのように感じられるよう、思慮深く、洞察に富んだ情報を提供します。
* ユーザーが自信を持って商談に臨めるよう、励ましとサポートの姿勢を示します。
===
もう、お分かりですよね?
ぼくたちがやるべきことは、「プロンプトのコツ」を暗記することじゃない。
ただ、自分のやりたいことをざっくり伝えて、あとは「ペンマーク」を押すだけ。



プロンプトが難しくて…と、AIに気乗りしなかった自分、よくがんばりました。もう大丈夫です。
【実録】素人の僕が、AIにプロンプトを作らせてみた結果…
「いやいや、本当にそんなうまくいくの?」
そう思う方もいるでしょう。
なので、実際にプロンプトを動かしてみた実例をお見せします。
上記の流れでできたプロンプトで、これから商談する企業の情報を調べてみました。
はい。僕が大好きなサッポロビールについて調べてもらいます。
サッポロビール、最高に美味いんですよね。大ファンです。(商談の予定はありませんw)
先ほど作成したプロンプトをそのまま打ち込んでみると、こうなります。
めちゃくちゃ優秀…!!
競合他社のリサーチも、一瞬でこれが出てきてしまいました。
プロンプトの素人が、やりたいことを書いてペンマークを押しただけです。
それだけで、こんなに質の高いコンテンツが、わずか数十秒で手に入ってしまった。
そして十分に良い回答をくれちゃってます。
この時、ぼくは確信しました。
「あ、時代はもう変わったんだ」と。
AIの進化に乗らない理由は、なにもありません。
プロンプトは学ぶな。AI活用の新常識。
今回の体験から、ぼくが学んだこと。
AI活用のコツは、
知識を「学ぶ」もの→「感じる」ものへと変わった
ということです。
かつて、ブルース・リーは言いました。
まさに、これからのAIとの付き合い方は、これなんだと思います。
安心してください。
どういうこと?とは自分でも思ってますよ。昔から例え話が下手です。悩んでます。
さておき、「プロンプトのコツ」を頭でっかちに学ぶのではなく、
- まずAIに作らせてみて、「うわ、すげぇ!」という感動を肌で感じる。
- AIに仕事をさせるための指示書(プロンプト)を、AIに書かせる。
この一見、ずる賢いループこそが、これからのAI活用のコツ・新しい常識になっていくはずです。

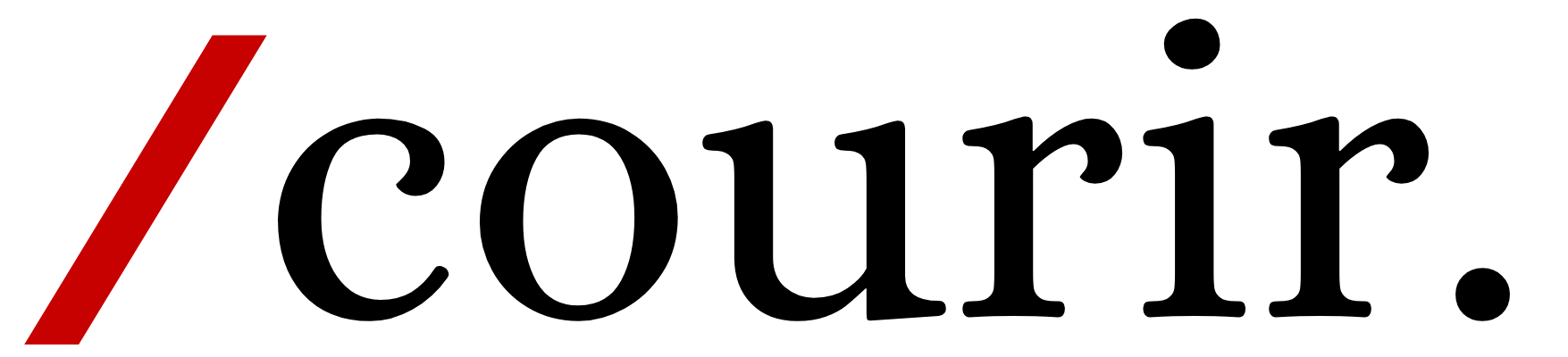




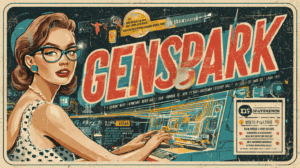



コメント